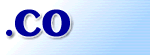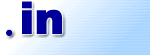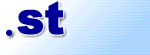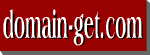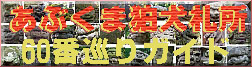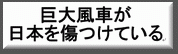Muse Scoreというフリーの記譜ソフトで作曲し始めた話はすでに書いたが、このスタイルでの作曲は今も続いている。
ひょんなことから、川内村時代に
関守まもちゃんからもらったネコの置物のことを思い出した。
うちに来たとき「こんなの、興味あるならどう?」と、ものすごく控えめな口調で差し出された。
「くれるの?」「もちろん」「じゃあ、ちょうだい」
……と、もらったのだが、そのときはあまり気にもとめなかった。
ネコが2匹、パズルのように合体したり離れたりするオブジェというかなんというか、小さな木製の置物。こういうもの自体はよくある。ああ、あの手のね、と、正直そのときは思った。
それがいかに傲慢な見方だったか、10年近く経った今、よく分かったので、懺悔の念を込めてこの日記を書いている。
関守は国道399号線から獏原人村に続く通称獏林道(県道でも村道でもないので、地図にも載っていない道)入り口に木工アート家具を製作する「獏工房」を構えていた。
「せきもり」というのは私が勝手に付けた呼び名。
夫のまもるさんはかつて獏原人村に住んでいた時期がある。その後、獏林道の入り口にあたる土地を購入して獏工房という木工アート家具の工房を構えた。
私たちが知り合ったときはすでに上の二人のお子さんは独立し、妻のじゅんこさん、すでに独立した上二人の姉兄とは年の離れた次男の三人で暮らしていた。
飾らない性格で、訥々と喋る人柄にいつもほっとさせられる。獏原人村の入り口、関所のようなところに住んでいるので「関守だね」と私が言ったときも「好きに呼んでくれ」と答えただけ。実際には本人がいないところでは(彼のほうが年上なのだが)親しみを込めて「まもちゃん」と呼んでいる。
(季刊「東北学」連載中『阿武隈梁山泊外伝』第2回より)
確か出身は静岡県で、親は地元で商売をしていた名士。息子に将来、政治家になってもらいたくて、選挙の時に投票用紙に名前が書きやすいよう「守」という簡単な1文字の名前をつけたんだと、これはたしかマサイさんから聞いた。本当かどうかは分からない。
田舎暮らしに憧れて都会から移住する人は多いが、
- 木工、陶芸、美術、写真など、アートっぽい創作活動を自然に囲まれた環境でしたい人
- 無農薬農業や自然食レストラン、カフェなど、自然をテーマにしつつ地域に根ざした暮らしをめざす人
- 豊かな退職金や資産を持っていてお金に余裕があり、老後を悠々自適に過ごしたい人
などが多い。
もともとその土地に住んでいた人たちとはたいていの場合価値観が違いすぎるので、衝突することもある。
特に農業関係では、農薬を拒否する自然農主義の人たちは、少しでも効率化できるなら農薬でも農業機械でも可能な限り取り入れようとする農家の人たちと対立する。農薬の空中散布や圃場整備、水利関連でぶつかり、それが原因で出ていく人の話もよく聞く。
「田舎で農業をしたいという移住者希望の人たちにとっていちばんのトラブルは水争い」だと、田舎暮らし専門の不動産屋さんたちはよく口にする。
まもちゃんは川内村に移住してからの歴史が長い。
初めて家を訪れる前にメールしたときの返事を今でも覚えている。
「いつでもどうぞ。ここは文化果つる地ですが」
文化果つる地……。そうなのだろうか。
その頃はまだ、阿武隈に残された自然の美しさや面白さが新鮮だったので、こういう場所にこそ、これからの人間社会にふさわしい文化が生まれ、育つのではないかという思いもあった。
しかし、時間が経つにつれ、確かに文化果つる地かもしれないなあ、とため息をつくようなこともいろいろ経験した。
田舎と都会の文化度の違いはどこから生まれるのか?
ひとつ言えるのは、本物を見極めて愛し、尊敬する精神を持っているかどうかが大きいということ。
テレビに出ている人、とか、○○大臣、とか、有名な企業に勤めている、とか、名前を知っている、とか、そういう人任せ、既成の知名度や評価にすっぽり乗っかって「すごい」「えらい」と態度を変えるのではなく、自分の目で見て頭で判断できるかどうか。それが「民度」であり「文化度」の違いだ。
まもちゃんはもちろんそれができる人だが、同時に、田舎に引っ込んで自分の価値観を信じて家具製作を続ける人生が、田舎からも都会からもきちんと評価されないであろうことを深く深く知っていた、覚悟していた、呑み込んでいた人だと思う。
まもちゃんの作る家具は本物だった。
憎まれ口を承知で書けば、阿武隈で生活していた7年間で、「これはすごいな」「これは本物だわ」と感心させられたものは少なかった。
アーティストを気取った作品や味自慢の料理なども、趣味の領域を超えていないものが結構あった。
見た目はかっこよくても使ってみるとすぐに取っ手がポロリと取れてしまうマグカップとか、ごついばかりで使いづらい椅子とかテーブルとか、歯ごたえのない蕎麦やラーメンとか、そういうものをいくつも見てきた。
まもちゃんが作る家具はそういうものとはまったくレベルが違う。
高価なので、うちには椅子一脚しかないのだが、この椅子のすごさは年月を経るに従って分かってくる。
木組みが細くて一見華奢、軽くてひょいと持ち上げられる。座面は麻紐から自分で編んでいる。これでちゃんともつのかなと最初は不安を抱いたのだが、購入して10年になるが、まったくガタがこない。麻紐の座面はネコののぼるくんがしょっちゅう爪研ぎをしていて、その度に叱るのだが、今も座面はビシッと締まったままだ↓

まもちゃんはすごいなあ。
まもちゃんからもらったネコの置物を改めてよく見ると、形が面白いのはもちろん、ネコの顔が実にいい。
で、注目してほしいのは、髭の表現が左右のネコで違っている点だ。
向かって左側のネコは凸部分が髭だが、右のネコは凹部分で髭を表現している。こういうところ、実はなかなか普通の職人さんでは真似できない。この表現がまもちゃんの思いつき、作っているときのアドリブだとすればすごいことだ。
アーティストは孤独な生き物だが、人生のどこかで「自分の価値観は結局のところ自分にしか分からない」と認識し、なおかつ「その自分にしか分からない価値観にはなんの意味もない」と悟ることになる。
そうして孤独はさらに深まるわけだが、その孤独に向き合ったまま死ねるかどうか、死ぬ勇気を持てるかどうかが、本物になれるかどうかの分かれ目なのだろうな、と、最近では思うようになった。
ネコの置物からなんだか息苦しい話になってしまっているけれど、このネコ、侮れない。
のぼるくんがしょっちゅう落っことすのだが、今もなくならず、傷ひとつつかずにこうして仕事場の片隅に鎮座している。
関守が言う「文化果つる地」にも興味深いイベントはたまにあった。
菜の花畑の真ん中にチェロ教室の先生と生徒たちを呼んで開く
「菜の花コンサート」。これは陶芸や木工をやっているしがさんという人が自分の土地を使って個人的に開催していた。呼ばれていたのは郡山市や福島市の「鈴木メソード」チェロ教室の人たち。

そのしがさんの家には、尺八奏者のブルース・ヒューバナーさんがよく泊まりにきていた。

ブルースは川崎市在住だが、福島の大学で講師をしていて、その行き帰りによく川内村を訪れていた。川内村で毎年行われる「天山祭り」というイベントにも何度か呼ばれていたようだ。彼と琴奏者のデュオ演奏会を富岡町まで見に行ったこともある。そのとき「最近、川内村ではやってないの?」と訊いたら、以前は天山祭りに呼ばれていたけれど、このところは呼ばれなくなったと寂しそうに答えていた。
その天山祭りは一度、雨天で会場が本来の天山文庫(カエルの詩人として知られる草野心平のために村が建ててあげた別荘)から村の体育館に移されたときに覗いたことがあるが、隅で警官たちが手酌でつまらなそうにカップ酒を飲んでいる姿を見て、なんだかすっかり興醒めしたものだ。(あの後、ちゃんと酔いを覚ましてから運転して帰ったのだろうか)
元川内村第三小学校校長のさとーこーちょーは遊びが大好きで、川内村の毛戸という富岡に近い地区に建てた立派なログハウス別荘にバンド仲間を呼んでコンサートを開いたり、元教え子たちなどを呼んで自然教室や
竹ドームハウス作りなど、次から次へと遊びを思いついては実行していた。

遊びを考案するのがうまいといえば、村の有名人・たかゆきさんは「山の幸直売所」というのを作って運営したり、そのそばにツリーハウスを作って遊び場にしたりしていた。

土木関係の資材や重機も持っていて、タヌパック阿武隈の入り口にある橋が落ちたときはすぐに駆けつけてくれて、格安で直してくれたりもする、親切で頼りになる人だったが、3.11の前に、突然、急性白血病になって死んでしまった。
昔、1Fで仕事をしていた時期があるとかで、僕らは当然そのことと関係があるのかなと思ったものだが、そうした話題は村ではタブーだった。
音楽イベントではなんといっても獏原人村で毎年8月に開かれる「満月祭」が最大のものだが、それのミニミニ版のようなものが「ロンパ舎祭り」で、毎夏、古殿町の山奥の廃校でひっそり行われていた。
2008年には、愛ちゃんに誘われて僕も行ってみたのだが、これは本当に楽しかった。
偶然にも、これを書いているときに、このとき一緒に会場にいたドラマーの人からフェイスブックで友達申請が来た。
あれからもう7年になる。3歳だった楽人にはその後二人の妹が生まれ、もうすぐ中学生。僕は還暦。
平凡な言い方だが、時が経つのは本当に早い。
こういう完全なアドリブセッションを日光でもやりたいとずっとチャンスをうかがっているのだが、なかなかやってくれる人が見つからない。
「俺たちは“曲”をやりたいんだから……」なんて言われてしまう。
僕自身がそれだけの技量がないし、技術のある人に甘えて一緒に遊んでと言うのは図々しすぎるだろうね。まあ、しょうがないか。
……と、とりとめもなく書いてしまったこの日記が、今年100ページ目になった。











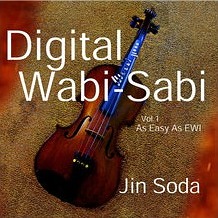


















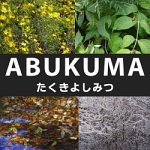
 『ABUKUMA』(全11曲)
『ABUKUMA』(全11曲)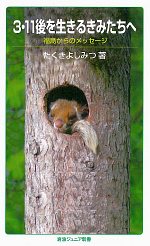
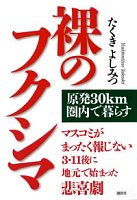
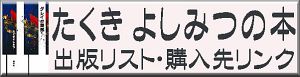

 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ