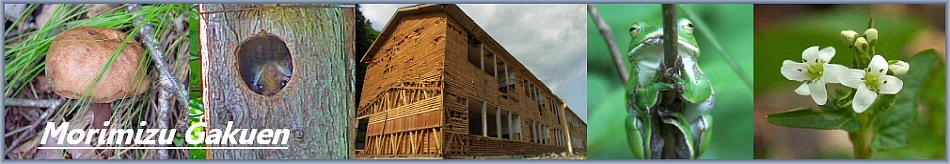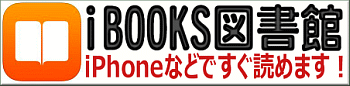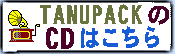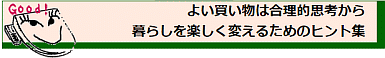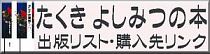野草や野の花のことにはとんと弱い、名前をいつまでも覚えられないあたしだが、最近はなぜか草の話題が増えているこの日記である。
しつこいようだが、さらに群生のことを考えてみた。
例えば、上の写真は我が家の隣地の現在なのだが、この風景、僕はきれいだなあと思う。
見えている白い花はフランスギク。毎年ここにいっぱい咲くが、僕はそれを楽しみにしている。夕暮れ時、踊り場の上の窓から見下ろすと、薄闇の中に白い花が揺れている光景は特に好きだ。
夕方、窓から見下ろすフランスギク
でも、雑草が繁茂していてみっともない。なぜ草刈りしないの? と思う人も多い。
感性は人それぞれだし、農家では事情もあるだろうし、一概にどうのこうのとはいえない。
同じ場所でも、毎年、繁茂する植物が変わることもある。
前の畑には今キツネアザミとオニノゲシが繁茂して盛んに綿毛を飛ばしているわけだが、去年までは気にも留めなかったから、多分、こんな風に一面に繁茂してはいなかったのだと思う。
それとも興味が向かなかっただけかな。
この畑は基本的にはほったらかしで、ときどき思い出したようにトラクターが入って耕し、蕎麦を撒いたりしているようだけど、そんな風に人間が手を入れる土地がしばらく放置されると何かのタイミングで何かがわ~っと生えてくる感じ。
それで思い出すのは2011年の川内村だ。
田んぼが作付け禁止になったため、水ははいらず、夏には草ぼうぼうになった。
あのときいちばん目立っていたのはメマツヨイグサだったが、秋が近づく頃にはセイタカアワダチソウも目立ってきた。
条件によっていろいろな勢力図が展開されるらしい。

2011年8月14日 川内村 田んぼにはメマツヨイグサが目立っていた
↓

2011年11月3日 川内村 セイタカアワダチソウが目立ってきた

2017年5月28日 我が家の玄関前 ドクダミが咲いた
ふと玄関の横を見たらドクダミの花が咲き始めていた。
これも場所によっては群生する。百合丘の庭にはびっしり咲いていたときもあって、きれいだなと思って見ていた。
ドクダミを見ると手放してしまったタヌパック百合丘を懐かしく思い出す。
でも、多くの人はドクダミをなぜか忌み嫌い、繁殖する前に始末しなくては……なんていってラウンドアップ撒いたりするんだよなあ。
こないだ食べてみたハルジオンはもう花期が終わり、今はだいぶ目立たなくなった。これからは丈が伸びるだけだから、近々草刈りしようと思う。
その程度のことなんだよね、本来、人の生活と野草の関係なんて。
困ったら対処すればいい、それまでは楽しめばいい……という程度の関係。
↑レオのお散歩の途中で、久々に通った場所でオオキンケイギクみっけ。でも、周囲がみんな刈り取られているのにここだけが残されているということは、草刈りした人がこの花を愛でるためにここだけは刈らなかったんだろう。
ま、そんなもんなんだよね。ここにオオキンケイギクが生えていたからといって、周囲の野原がオオキンケイギクだらけになるなんてことは、ここではまずないだろう。
ナガミヒナゲシだって、他のいろいろな草花に混じって、なんだか肩身が狭そうに咲いているくらいだから。
ハルジオン、キツネアザミ、フランスギクの群生は、それなりに見ているだけで楽しい。畑に生えたやつはどうせトラクターが入って一網打尽にされる運命だし。
 一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ
一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ