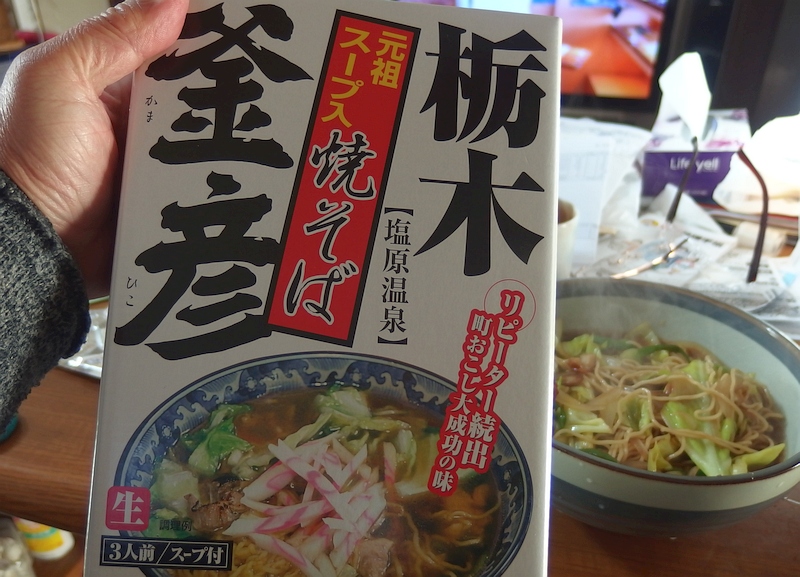今日はホームでクリスマス会みたいなことをやるというので、音曲係としてギターとEWIを持って出かける。
若い頃は友達の結婚式で歌うのさえ拒否したものだったけど、あたしも大人になったというか、枯れてきたというか……。
着いたら、スタッフのSさんが、娘が熱を出したから連れて帰るといって、入れ違いになった。
施設長といちばん若いEさんの二人がパタパタと仕事をしている。中央のリビングにはおばあさんが5人と親父。
2人は畳の上に横になって動かない(死んでいても気づかないかも……)。2人はほとんど表情を動かさないけれど、うち1人は少し反応してくれる。もう1人は「いろんな楽器があるんだねえ」とかパラパラと拍手してくれたり、反応がある。親父一人が機嫌よく、英語でSilent Nightを歌ったりしてた。

みんなそれぞれのペースで、楽しんだり、寝ていたり、スタッフは背中で聞きながらせっせと台所で仕事していたり……いつものことだけど、とってもゆる~い空気。
その間も、ひとりがトイレに行こうとすると、スタッフがサッと気づいて介護して、終わると知らないうちにまた戻ってきて……プロだな~、って感心する。
親父はほんとに幸運だ。今はもう満室で入れない。
施設長に訊いたら、入居希望者は何人も来るのだけれど、費用を払えないといって諦めるのだとか。都会の感覚からすると、20万円以下なら高いとはいえないけれど、田舎ではそんな額を年金でもらっている人はほとんどいないのだろう。特に女性は。
高度成長期にサラリーマンをしていた親父はそこそこの年金を受給しているので、なんとか今は支払いができる。施設としても、経営はかなり厳しいらしいけど、なんとかこのまま続いてほしい。
帰り道、昔、井津先生にいただいた手紙の一節を思い出した。
きみの「四畳半の音楽活動」は、すばらしい意味を持つように思われます。
専制政治家のように大衆にはたらきかけることを、私はあまり評価していません。それはおそらく空しいことであり、時に害悪でさえありましょう。
私は「一人に向かって」をモットーに生きていくことにしています。その方が結局は普遍性を獲得すると思います。こうして、きみ個人に向かって長い手紙を書いているのもそうだし、学年全体の生徒に話すときでも「一人に向かって」話すつもりで話すようにしています。「九十九匹の羊を置いて一匹の羊を探せ」というキリストの逆説をこのように応用しているわけです。
経済的な価値観では数の多いことを価値あることとしますが、数が少ないほど価値のある世界というものがあることを私は信じています。成績不振の少数の生徒、クラスでいじめられがちな一人の生徒、精神分裂症の一人の教え子、文学好きな一人の少年、特別養護老人ホームの一人の老人、障害者同士結婚した一組の若い夫婦、といった人々に向かってじかに話しかけます。
このじかのつき合いほど重たいものはありませんが、嘘のはいり込むことの少ない世界ですから、私には向いているように思います。
先日も、生徒たちと一緒に作った手づくりの紙芝居をもって特別養護老人ホームへ行ってきました。
心身障害者が多く、彼らの半数ほどはほとんど人間的な反応を示しません。
拍手喝采を受けないのですから、ある生徒は、やりがいのなさを感じたかもしれません。しかし、大切なことは喝采の物理的な音量ではないのです。数字の多さ以外の何かが尊いのです。その何かをじかに感じればよいのです。それを言葉で規定する必要はありません。きみの音楽活動が私のこんな考え方に幾分でも接点を持ちうるものでしたら、陰ながら声援を送りたいと思います。この考え方は、きみが有名になることを妨げるものでは決してありません。少数の人に向かって語りかけた結果が、多くの人に認められることになったというのでしたら、そんなめでたいことはありません。
手紙の日付は1991年8月6日。
もう四半世紀以上前のことなのか……。
正直、この手紙を読んだとき、生徒と一緒に特養を訪れた話など、自分には一生縁がないと思って、若干の違和感を覚えたような気がする。
でも、それから26年が経ち、今こうして、誰も反応してくれないだろうと分かった上で、老人たちの前で演奏している自分が、なんとも不思議というか、複雑な気持ちになる。
これは僕の音楽とは関係なく、たまたま僕がちょっとギターが弾けるとか、変わった楽器を持っているということで、手伝いをする……ということなんだけれど、若いときは自分がそういうことをすること自体、想像できなかった。
今は、いろんなことに対して、ゆる~く接することができるようになった、ということかなあ。
ようやく手の空いた施設長が部屋に来て、僕にいろいろ質問してきた。どんな子供時代だったのかとか、親父とはどんな風に接してきたのかとか。
子供の頃は、自分は人間ではなく、選ばれた特別な存在で、自分だけは死なないんじゃないかと思っていた……とか、そんな話をしたら、へえ~、と興味深そうに聴いていた。
そのうち、施設長も自分の子供時代の話をしだして、その内容がまた結構強烈で……、その横ではおばあさんたちが死んだように寝ていたり、無表情で座っていて……。え? これがクリスマス会なの??
でもまあ、考えてみると一般の家庭ではこういうのが「普通のこと」なんだよね。誰かが話を始めたらそれに引っ張られて場が和んだり、ときには喧嘩になったり。それが普通。
でも、そんな風に自然体で暮らしていける介護施設は極めて少ない。介護スタッフは「お仕事」としてルーティーンワークをこなし、入所者は「介護される人」という扱いを受ける。自分が「普通に扱われていない」と感じる入所者は、絶望したり、ストレスをためたり、スタッフに気を使ったり……。
介護施設で幸せに死んでいくのは本当に難しいことだと思う。