今まで石仏にはほとんど興味がなかったのだが、小説版『神の鑿』を書くにあたっていろいろ勉強しているうちに、石仏そのものよりも、石仏から見えてくる江戸時代の人びとの世界観や暮らしぶりに興味がわいてきた。
ご近所でいちばん謎なのが「福耳薬師」と名づけたかなり大きな石像。年代が今ひとつ分からないのだが、もう一度確認しにいってみようと思い、ライチェルを連れてかなり長いお散歩に。

かなり大きい。


100円供えられている。太っ腹だなあ。

薬師如来像には年号が見あたらないのだが、右隣の燈籠は享保12(1727年)年とある。

その燈籠の文字は「奉建立不動尊」と読めるのだが、不動明王像は見あたらないなあ……?

これは享保4(1719)年や享保3(1718)年の燈籠もある。300年前!だ。


いい感じのデザイン。

隣は地蔵菩薩かと思ったが、「菩薩」には螺髪がないということで、なんでしょね。阿弥陀如来? いずれにせよ、お顔がとてもいい。


周囲の石仏はどれも年号が摩耗していて読めない。強烈な逆光だし、今度また出直すかな。


十九夜講とか女人講という文字が微かに読める。この土地は女人講が盛んだったようだ。



文政8(1825)年。亨保年間に比べると100年後だから、周囲の石造物の年号から薬師像や地蔵像の年代を推理するのは難しそう。

薬師像はもともと台座がもう少し高かったそうだ。今市地震で石が割れてしまい、その分だけ低くなったとか。それでもこれだけの高さ。隣の地蔵の台座は、おそらく後から薬師像に合わせてかさ上げしたのではなかろうか。

そしてこの木像の十二神将も謎だなあ。いつからあるのだろうか。

300年前の人たちが奉納した石造物群。全国にこういうものがたくさん残っているのだろうが、今となっては、謎だらけだ。雪が少ない男体山を見ながら帰る。

 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ




























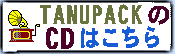
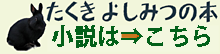
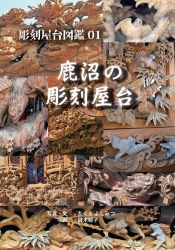
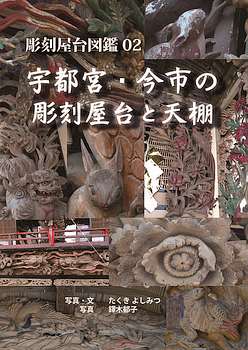
 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ