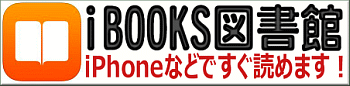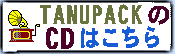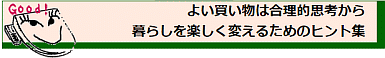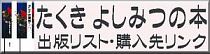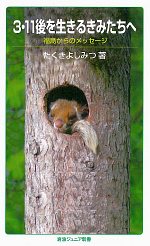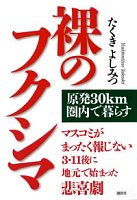上智大学でJVC(ジャパンボランティアセンター)の母体を作り、その後、国連職員になって難民救済活動を生涯の仕事にしてしまった友人Sくんからメールが来て「今、テヘランにいるんだけど、今度、日本に戻ったときにきみがもっていたようなハンディなギターを買って帰ろうと思ってる。シリーズ名を教えて」とあった。
前にうちに遊びに来たときに見た僕のギターのことをずっと覚えていたらしい。さて、どのギターのことだろう。
うちにはエレガットしか置いてないのだが、Sくんがほしいのは多分鉄弦のギターのはず。
「ハンディなギター」の意味がよく分からなかったので、「安くてもしっかりしているという点では
Crafterなんかいいんじゃない?」と答えておいた。
Crafterは
3年前のちょうど今頃、衝動買いで2本買ってしまったのだった。
最初はソリッドのエレガット


、
間髪入れずに鉄弦のセミアコ


どちらも今までの僕のギター購入歴からすればとんでもなく安いギター。だからまあ、気楽に買ってみたのだが、特にエレガットは大当たりで、弾きやすく、作りもしっかりしていて、居間の柱にぶら下げて練習用にしている。
で、そのCrafterのエレガットの内蔵チューナーが壊れてしまった話は書いた……あ、書いたよね。
プリアンプごと入れ替えられないかと探し回ったけど無駄だった、と。
それでトラップにはまってしまって、ZOOMのエレアコ用エフェクターを買ってしまった……と。
今回は、Sくんに勧めるギターを探しているうちに、Crafterよりさらに安いエレガットを見つけてしまった。
それがIbanezの
 GA37STCE
GA37STCE
というモデル。
値段とスペックを見てちょっとびっくり。
たかだか3万円なのに表板は単板。しかもネックは僕の大好きな46mm幅。14フレット継ぎ。この46mm&14フレット継ぎというのは、僕のメインモデル松子(茶位幸信工房に特注したたくきスペシャルモデル)と同じ。胴の厚さもほぼ同じ。横裏はさすがに合板だが、これで3万円? そんな値段で売っているということは、原価はいくらなのよ、とびっくりしてしまった。
で、眺めているうちに、実際に弾いてみたくなってきた。
松子はプリアンプ内蔵モデルではないし、万が一にも壊したくないので宅急便で会場に送ったりしたくない。野外のライブでも使いたくない。
杉作とアントニオはネックがクラシックギターと同じなので、ちょっと弾きづらい。
Crafterは生音が出ないので、練習にはいいけれど、ソリッドだから重い。
……それらの条件を全部中和して妥協点をうまく見つけたようなギターではないか。
しかも、Dark Violin Sunburstという、黒っぽい塗装のがある。こういう黒っぽいギター、いいなあと思いつつ、でも、塗装が濃い色のやつは木目が荒れている板を使うんだよなあ……きれいな板を選んで使っているのがクリア塗装……ってことで、今までは避けていた。これだけ安ければ板の木目なんか多少荒れていても関係ないや……とか、いろいろ思いを巡らしてしまい……半日うなされた後についにポチしてしまった。
「残りの人生、長くはないのだから、こんな経験を3万円でしたと思えば……」
そのときの罪悪感たるやもう……必要ではない安物をなぜ? おまえはバカか……と、すごい自己嫌悪に陥る。
階下にフラフラと降りていき、ため息を漏らしたところを助手さんが見逃さず、即、言い放った。
「どうしたの? ……あ、ギター買ったんでしょ!」
う・う・う……。
もう、呻くしかないじゃないの。
「買ったんでしょ。1本買ったなら、1本捨てなさいね。邪魔だから」
……バカ言ってんじゃない。捨てていいギターなんてあるわけないでしょが。どれも高級品の傑作なんだから。
……というわけで、印刷所から予定より5日も早く届いた年末状と一緒にクロネコが持って来たアイバニーズのエレガットが↓こちらでございます。

たまたま録音中で使っていたCrafterのSAシリーズの隣に置いてみた

いかにも安っぽいといえば安っぽいのだが、よくできているよなあ……ポジションマークの位置なんか
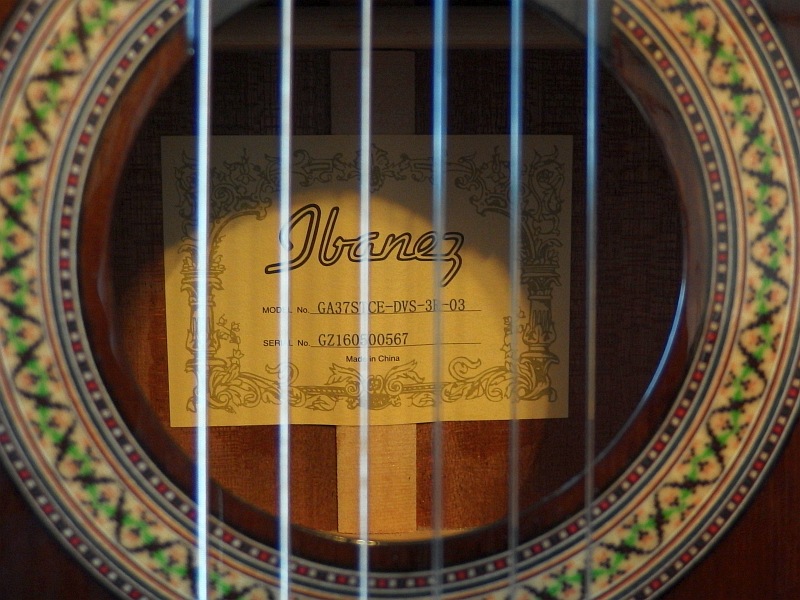
燦然と輝くMade in Chinaの文字……潔い

ダークサンバーストっていうカラーリング。初体験。真っ黒でもよかったんだけどね。なんか演歌歌手っぽい感じもあるよね、これ

ボディはこの厚さ(薄さ)で、杉作や松子と同じレベル。プリアンプの取り付け位置がお尻寄りなのが面白い

これもチューナー内蔵で便利。Crafterのようにポッチが壊れないといいのだが……

ネックが微妙に波打っているようにも見えるのだが、実際に弾いてみた感じはなんともなかった
さて、弾いてみた感じは……。
ネックの幅と14フレット継ぎゆえの弦圧の低さはとてもいい。弾きやすい。でも、欲を言えばネックはフラットではなく、ちょっとだけラウンドさせてほしかった。そのほうがより弾きやすくなっただろう。
あと、微妙にネックが厚い。これは松子が異常に薄いネック(今はもう輸入禁止で手に入らないホンジュラスマホガニー製でトラスロッドなし)なのに慣れているせいもあるかもしれないが、安いギター特有のぼてっとした感触がちょっと残念。
それでも普通のクラシックギターのネックなんかに比べたらはるかに弾きやすいわけで、十分にOK。
音は、生音、ライン出力のどちらもマイルドというか、芯があまりない音。よく言えばクラシックっぽいまろやかさがある。
これはまあどうでもいいんだわ。3万円のギターにこれ以上期待しても無理だし。
特注の松子や杉作、スペイン製のアントニオはみんなオール単板で値段も一桁違うのだから、生音がこれと変わらなかったら逆に困る。
野外ライブやエフェクターをかませてのライブ演奏などでは、どうにでも音作りできるから、これでOK。
とにかく値段に驚くよね。3万円!
こんなギターが40年前にあったらなあ。あの頃の日本製のギターなんて、ろくなもんじゃなかった。3万円ではオール合板があたりまえ。造りも雑で、ネックはすぐに反ったし、ブリッジは剥がれるし……。
ギターが手工業から管理された工場大量生産時代に入って、むしろ低価格の楽器は品質が飛躍的に向上したのだろう。
時代は変わる……ボブ・ディラン……。
ともあれ、これは文句なくお勧め。
ちなみにSくんが言っていた「ハンディなギター」というのは、ボディのないサイレントギターのことだった。
それなら
⇒こちらですよ


 一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ
一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ
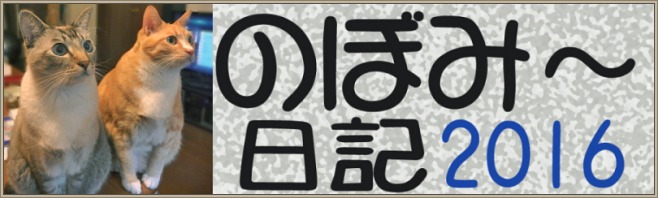
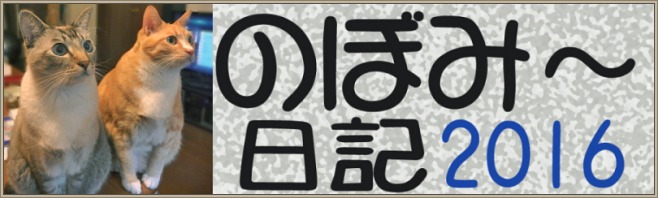


 GA37STCE
GA37STCE

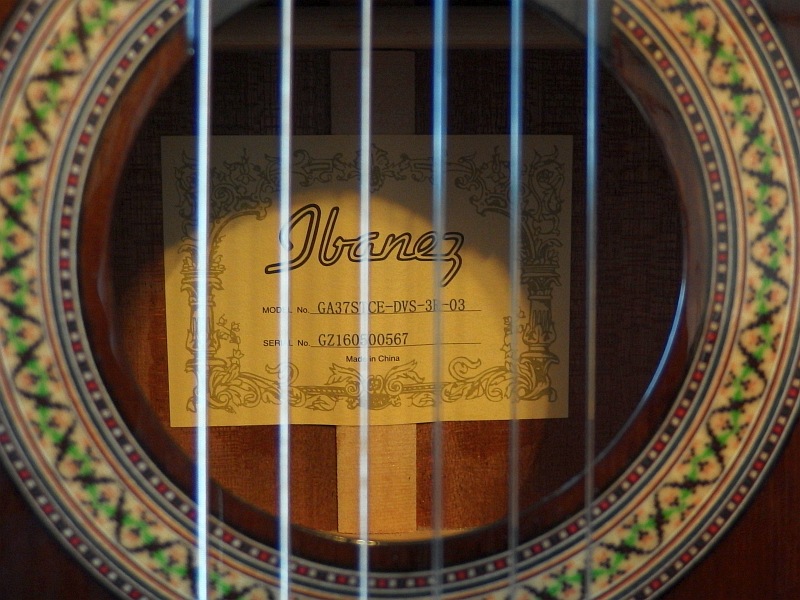









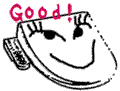 よいお買い物
よいお買い物