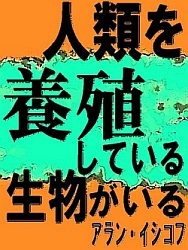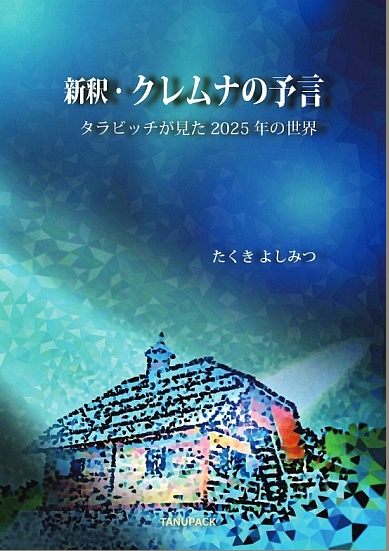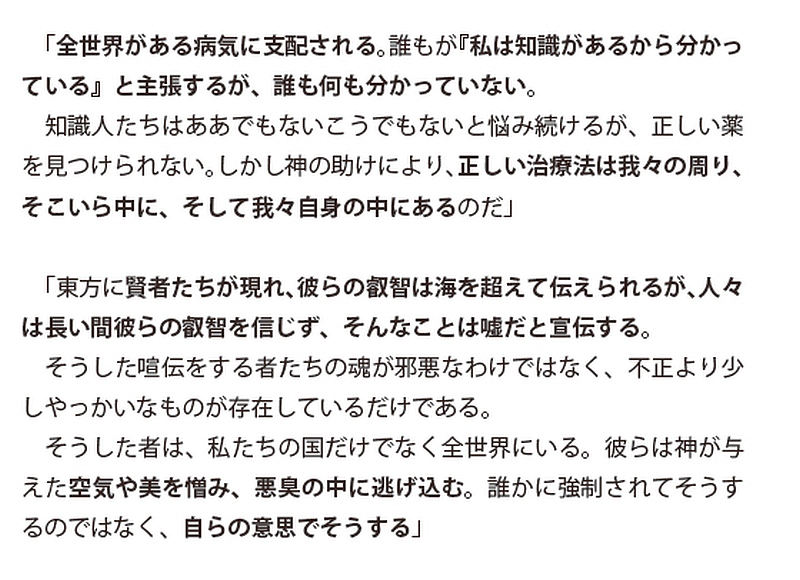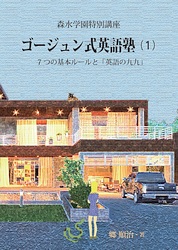助手さんが、玄関前の植え込みによく分からない植物が生えてきたので撮って、という。
もともとはシロヤマブキを植えてあるところに、ヤマイモが生えてきて絡みついていたのだが、そこにさらに蔓性で青い実をつけた植物が絡んできた。

↑第三の謎の植物の花

↑謎の植物の葉っぱ
フェイスブックに写真をUPしたところ、イヌツゲ、サワフタギ、野ブドウ、アオツヅラフジ、カミエビなどのコメントがついたので、片っ端から調べてみたところ、アオツヅラフジ(別名カミエビ)らしいと判明。
北海道、関東地方以西〜沖縄の低地の草原や道端、林縁などに生える。枝は淡黄褐色の毛が生える。つるは右巻き。葉は互生。葉身は長さ3〜12cm、幅2〜10cmの広卵形〜卵心形。葉の形は変化が多く、ときに浅く3裂する。(略)
別名カミエビ 花期は7〜8月。(樹に咲く花)
子房が6個の心皮に分かれ、花後に心皮が離れ、各々が1個の果実になる。
学名は、Cocculus trilobus
ツヅラフジ科アオツヅラフジ属
似たものにツヅラフジがあるが、葉柄が長く、茎や葉が無毛。
(松江の花図鑑 より)
秋、ブドウのような果実が鮮やかな藍色に熟す頃が一番目立つ。ただし果実は有毒なので注意。(森と水の郷あきた より)
……ということなのだが、さらに調べていくと、
こんな興味深い記述を見つけた。
私は今植物学界の人々ならびにその他の人々に向かってアオツヅラフジの名を口にすることを止めよ! と絶叫するばかりでなくそれを止めるのが正道で,止めぬのは邪道であると公言することを憚らない。何んとなればツヅラフジ科のCocculus trilobus DC.(=Cocclus Thunbergii DC.)は断じてアオツヅラフジではないからである。
しからばそのアオツヅラフジとは一体どんな植物か,すなわちそれはアオカヅラ(『本草和名』,『本草類編』,『倭名類聚紗』),一名アオツヅラ,一名アオツヅラフジ,一名ツヅラカヅラ,一名ツヅラフジ,一名ツヅラ,一名ツタノハカヅラであって普通にはツヅラフジと称える。すなわちこれを学名でいえばSinomenium diversifolium Dielsで,もとはCocculus diversifolius Miq.と名づけられたものだ。
(牧野富太郎『植物一日一題』 1953年)
つまり、
牧野博士によれば、アオツヅラフジはツヅラフジと呼ばれる植物の別名の一つで、江戸時代の有名な本草学者が間違った記述をした為に一般的になってしまったが、本来は昔から使われているカミエビの名前であるべきとの主張である。
カミエビは 「神のエビヅル」を意味し、エビヅル(エビカズラ)はヤマブドウの一種で6月に花を咲かせ、秋には食べられる果実を付けるが、アオツヅラフジの果実とエビヅルの果実が似ており、薬効あらたかなので「神のエビヅル」からカミエビと呼ばれたようである。
(「野の花散歩」より)
しかし、この説は受け入れられなかったようで、富太郎の死後にも改定・重版を重ねている『原色牧野植物大圖鑑』でも、1997年発行のものには「アオツヅラフジ(カミエビ、チンチンカズラ、ピンピンカズラ)」「ツヅラフジ(ツタノハカズラ、オオツヅラフジ)」として載っている。
また、「カミエビのカミは神のことで,エビはエビヅルに基ずいた名であろう。一名をピンピンカズラ,チチンチンカズラというが,これは,多分つるを張りつめてはじくと音を出すので,これに基ずいたものであろう。」(『牧野新日本植物図鑑』1961年版)とも書いているが、これにも異説があり、
エビはブドウの古名で、果実に白い粉がふいているのをカビに見立てて「カミエビ」と呼んだ。(森と水の郷あきた)
という解説もあった。
神なのかカビなのか……?
牧野富太郎はトンデモ人間だった
牧野富太郎といえば、今、NHKの朝ドラ「らんまん」のモデルになっているので、にわかに注目されている。
助手さんは玄関前に生えている「ヘクソカズラ」を見て「ひどい名前よね。牧野富太郎なら絶対にこんな名前つけなかったわよね」と言っていたが、

↑ヘクソカズラ
実際には、オオイヌノフグリ、ハキダメギク、ワルナスビ、ムカデラン なんていうのも富太郎の命名らしい。
(オオイヌノフグリはすでに江戸時代から「いぬのふぐり」と呼ばれていた植物の近縁種であるということから「オオ」をつけただけらしいが……)
で、その牧野富太郎の実像を探る人が増えて、ネット上でもいろんな話が出てきた。
実際の富太郎は「天真爛漫」なんて言葉では表せないほどぶっ飛んだ性格の人間だったようだ。
そのぶっ飛びぶりをいくつかまとめてみると……、
- 富太郎19歳のとき、許嫁だった3歳下の従姉・山本猶(なお)と結婚。しかし、実家の酒屋は祖母(富太郎の祖父の後妻なので血はつながっていない)と番頭に任せ、3年後には妻を残して上京し、東京大学理学部植物学教室の矢田部良吉教授を訪ね、特別に教室への出入りを許される。しかし、大学から持ち出した高価な本をいつまでも返却しなかったり、トラブルメイカーでもあった。
- 25歳のとき、菓子店で働いていた当時14歳(!)の小澤壽衛(すえ)と同棲を始め、翌年には長女・園子が誕生。今で言えば女子中学生を妻帯者がたぶらかして一緒に住み始めて、即妊娠させた、ってことだわね。その後、壽衛は54歳で死去するまでに13人の子を産んでいるが、無事成人したのは3男4女の7人だけ。他の6人は早世して名前も定かでない。
- 妻が第2子を身ごもっているとき、実家の倒産整理のために単身故郷の土佐に戻っているが、そのときも高級旅館に泊まり、西洋音楽の演奏会に興じるなど、金銭感覚が完全におかしいままだった。その間に長女・園子が死んでいる。
- 実家の倒産の一因は、最初の妻・猶が富太郎にせびられるまま研究資金を提供し続けたこと。猶は夫の富太郎から「同棲している女に子供ができた」と告げられると「おめでとうございます」と言ったとか。その後も壽衛とは何度も手紙でやりとりをして援助していた。酒屋が倒産した後は四国のどこかにひっそり渡って生涯を終えたとか。
- 一方、13人の子を産んだ壽衛は、富太郎の研究費と家計のためにありとあらゆる金策を続けたが間に合わず、ついには「待合茶屋」(芸奴を呼んで遊ぶ店。遊郭的な性質もあり、富豪や政治家の密会や談合場所にも使われた)の経営を始めて成功する。その金で富太郎の研究を援助したが、富太郎は「妻がそんな恥知らずな商売を始めたことは自分があずかり知らぬこと」みたいな態度だったらしい。
- 目立ちたがりでサービス精神旺盛。当時の人間としては残っている写真が非常に多くて、ほとんどが笑っている。話もうまかった。
- 富太郎は94歳の長寿だったが、死ぬ間際にも介護していた看護師に「きみは美しい」などと言っていた(その場にいた孫が証言している)。生前つけていた「面白川柳」というノートには「性の力の尽きたる人は呼吸をしている死んだ人」という歌も残されている。
斎藤 美奈子氏がドラマが始まる前にすでに書いている
⇒コラムが面白い。
植物学者としての名声もさることながら、牧野富太郎は並外れて型破りな人生を送った人物としても知られている。たしかにドラマの主人公にはぴったりであろう。だけど家族はたまったもんじゃないよな、というのが私の嘘偽らざる感想である。
(略)
猶を実家に残したまま、牧野が寿衛子と所帯を持ったのは祖母が他界した二年後だが、祖母亡き後も、牧野はしょっちゅう旅費だ自費出版の費用だと実家に金の無心をしている。それを差配したのは、事実上の家長として岸屋を仕切る猶だったはずだ。『草を褥に』には、送金をめぐる寿衛子や猶の手紙が引用されている。一方『自叙伝』が書く実家との関係は……。
〈私の二十六歳になった時、明治二十年に祖母が亡くなったので、私は全くの独りになって仕舞ったが、しかし店には番頭がおったので、酒屋の業務には差支えはなく、また従妹が一人いたので、これも家業を手伝い商売を続けていた。しかし私は余り店の方の面倒を見る事を好まなかった〉。猶はただの従妹扱いかい。
(牧野富太郎を支えた「二人の妻」をめぐって より)
……たしかに「家族はたまったもんじゃないよな」である。
3歳下の従姉を妻にしながら実家を出てしまい、実家はただのATM代わり。
妻帯者でありながら、菓子屋の店先に立つ14歳の少女に一目惚れして同棲を始め、すぐにはらませてしまう。14歳というと今なら中学生よ。(15歳としている資料もあるけれど、当時は数え年で年譜を書いているから、今の満年齢なら14歳で合っていると思う。同様に富太郎の没年齢も96歳としている年表が多いが、これも数え年なので満年齢は94歳である。1862年5月22日〈文久2年4月24日〉- 1957年〈昭和32年〉1月18日)
しかも、その後も寿衛は20年ほどの間に13人も懐妊! 最後は子宮関係の病気で亡くなったらしいが、無理もない。
それにしても、富太郎は植物採集旅行などで家を空けることも多かっただろうに、いつそんなに仕込んでいたんだろう。
ドラマではとんでもなく嫌なやつに描かれている田辺教授(谷田部教授がモデル)にしても、富太郎の自己中心ぶりに我慢ならなくなったのだろうなあ。
富太郎の人生に親父の人生を重ねてしまう
普通に考えれば「牧野富太郎ってとんでもないやつだったんだな」と思う人が多いだろうが、私としては親父(故人)の性格にそっくりなところがあって、なかなか感慨深いものがある。
研究者タイプの人間には、確かに「こういう人」はいるのである。
困った性格だが、不思議と人から愛されるタイプ。
私の親父はまさにそういう人だった。
昭和3(1928)年生まれの親父は、陸軍士官学校在籍中の16歳のときに終戦となり、その後は師範学校で理科と英語の教師免許を取得。福島市内の中学校を経て、福島大学附属中学校の理科教師に赴任した。
幼い頃から絵がうまく、尋常小学校時代から大人顔負けの絵を描いていた。当人も将来は画家になるという夢を持っていたようだが、戦争や貧困でその夢は潰えた。
理科教師としての親父は感情の起伏が激しく、理科室でビーカーを壁に投げつけて壊す事件など、いろいろ大変な面もあったらしいが、教室での教え方がうまく、生徒からは人気があったそうだ。
その附属中学校で、子持ちの人妻である養護教師に一目惚れしてラブレターを書いたり、詩を書いたりして口説いていた。
その子持ちの人妻の「子」というのが私である。
お袋は夫(私の実父)との相性が悪く、私が4歳くらいのときに離婚、その後、親父とのつきあいを続け、再婚が許される1年を経て再婚した(女性は離婚後1年間は、妊娠していた場合、再婚相手の実子かどうか証明が難しいという理由で再婚を認められなかった)。私が親父の養子となったのは小学校入学後の6歳7か月のときだった。
親父は血のつながっていない私と、最初は多少ギクシャクしていたが、基本的には優しく接してくれて、中学受験のときは、天体のことや力学関連のことも実にうまく教えてくれた。おかげで入試でも理科は絶対の自信を持って臨めたし、実際にほぼ満点だったと思う。
中学生のときは、夏休みの自由研究では植物採集や昆虫採集のやり方を教えてくれた。年季の入った親父の
胴乱をかついで野山で植物採集をし、その後、標本の作り方も教わった。本格的なその植物標本は、夏休みの自由研究課題作品として校内で「金賞」を受賞した。
高校生のとき、美術部にいた同級生に誘われて写生に連れ出されたときも、親父の使い込んだイーゼルと絵具セットを借りて持っていった。私にとって、油絵というものを描くのはそのときが初めてだった。
私は絵を描くことは苦手ではなかったが、とにかく杜撰で、仕上げが甘い。描いている先からすぐに飽きてしまい、そのときも6割くらい描いたところで放りだして、一人、付近を散歩していたのだが、その間にたまたま通りかかったどこかの老人が、友人の隣りに置いてあったイーゼルの絵を見て「これは君の先生の絵か?」と言ったそうだ。絵の出来よりも、道具の年季の入り方からそう思ったのだろう。
使い込んだ胴乱やイーゼルの他に、親父の持ち物としては、父親(
鐸木三郎兵衛の三男・巌)の遺品としてロイヤル社のタイプライターや革製の旅行トランクなどを覚えている。どちらも大正時代くらいの骨董だが、私はそのタイプライターで実際にタイピングの練習をしたし、革製のトランクを持って旅行もした。

祖父・鐸木巌の遺品 革製のトランク
親父はとにかく凝り性で、しかも要領が悪い。人の何倍もの時間をかけて作業をする。
お袋と結婚後、教師を辞めて一緒に上京し、お袋が知人に頼み込んで大手出版社に編集者として途中入社したのだが、そこでの仕事ぶりもていねいさが尋常ではなく、他の社員が全員退社した後も毎晩終電ギリギリまで会社に残って仕事をしていた。同僚からは嫌がられただろう。
凝り性と浪費癖は合体していて、独身の教師時代は市営住宅の長屋に母親と姉と3人暮らしだったが、中学校で冬にスキー教室を開くことになると、金がないのに東京に出て、スキー靴専門店に自分の足に合わせた靴を特注した。
ところがそのスキー靴が特注なのに小さくて合わないと知ると、お袋(職場の同僚である子持ちの人妻)に「これあげる」とプレゼントし、自分用には再び上京して靴を作り直した。一体どれだけの金をつぎ込んだのか。
本も大量に買い込み、長屋には植物図鑑、動物図鑑だけでなく、昆虫図鑑、クモ類図鑑まで全巻揃えていた(将来はクモを専門に研究するという希望もあったらしい)。さらには世界文学全集、日本文学全集も全巻揃えて持っていた。
お袋と結婚後は、お袋が強くて親父の給料をすべて管理していたのでそうした金遣いはできなくなったが、お袋が先に死んでからはダムが決壊するが如く、ありとあらゆる趣味的物品に金をつぎ込み、交際費や衣服(ファッションというか……)にもいくらでも金を使い、気がつくと数千万円あったはずの貯金がゼロになっていた。
認知症も発症していたので、貯金ゼロの親父の介護は私たち夫婦にとっては大変だった。
そんな親父を看取って4年以上経った。
牧野富太郎の生涯を知るにつれ、どうしても親父の人生と重ねてしまうのだ。
親父は自然科学系の研究者になるべき人だったと思う。しかし、時代や環境がそれを許さなかった。
それ以上に、自分の個性を上回る強さを持った子持ち人妻に恋をしてしまったために、それ以後の人生が大きく変わった。お袋が親父の人生を乗っ取ってしまったようなところがある。
もしも親父が、猶や寿衛のような女性と結婚していたら、会社員にはならず、研究者、あるいは教えるのがうまい理科の人気教師という人生を送っていたのではないだろうか。
しかし、そうなっていたら、私の人生もずいぶん違っていたかもしれない。
私は親父が稼いだ給料で大学まで行かせてもらったのだから。
また、親父は牧野富太郎とは違って、女性に対する敬意を持っていた。晩年は短歌の会に出入りし、多くの女性たちから愛されていた。
仕事に没頭すると誰も寄せつけないようなところがあったが、一方では誰からも愛されたいという願望もとても強かった。その表現が下手なので、お袋からは相手にされていなかったが、私はそんな親父を不憫に思うことがよくあった。
「しゃあないなあ」と呆れることが多かったが、憎みきれない。子供っぽい面や弱さもある人間味が好きだった。
いろいろ大変なことはあったけれど、少なくとも私と親父の相性は、お袋との相性よりもずっとよかったように思う。
私がペンネームを「たくき」としているのも、親父に育ててもらったことに対する義理から「鐸木」という姓を残したのだった。
……ん?
牧野富太郎の話じゃなかったっけ……。
まあいいや。こうして故人のことを振り返るのも供養のうちだろう。
そうそう。これが今年100回目の日記である。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ