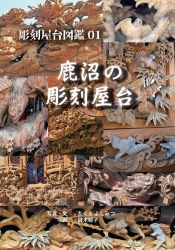2017/11/12
(およそ10ページ分、飛んでいますが、11月26日以降に公開します)
宇都宮に彫刻屋台2台を見に行く(1)仁良塚屋台

鹿沼の駒場さんから彫刻屋台お披露目情報メールがきた。仁良塚屋台と白沢甲部屋台という2台がお披露目されるというので、早起き(9時半で??)してでかけた。
まずは仁良塚屋台。
国本地区のお祭りに合わせて展示されていた。
配布されていた説明書きや宇都宮市立図書館作成の「宝木地域データブック」(2016年11月)によれば、
二宮尊徳が設計、指揮した宝木用水(徳次郎付近では「新堀」、宇都宮の宝木地区では「宝木用水」、さらに下流では「新川」と呼ばれる。嘉永5(1852)年に完成)を開削するにあたり、村民の団結と絆の証として、地元の大工棟梁「岩崎重右衛門」が造った天棚(車輪のない二層式のもの)が大元であるという。
その天棚に嘉永7(1854)年頃から本格的に彫刻が施されるようになり、安政2(1855)年に完成。
その後、大正13(1924)年に大工棟梁・中山銀蔵が、天棚の唐破風・紅梁・彫刻等を利用して車輪付きの屋台に改造。豊國神社の祭礼などで仁良塚地区内を挽き回しするようになったという。
その後、戦争を挟んで長い間、分解されたまましまわれていたのを、平成3(1991)年に仁良塚公民館新築に合わせて仁良塚まつりが開催となり、40年ぶりに屋台も組み立てられ、平成6(1994)年には組み立てたまま収納できる屋台蔵も建築。鹿沼市の彫工・黒崎嘉門(孝雄)氏に依頼して、平成24(2012)~25(2013)年にかけて彩色・補刻を行う大改修。今の姿になった。
展示脇にあった解説パネルの写真をお借りして、改修前と改修後を比べてみよう。

↑改修前 改修後↓



改修前↑ 改修後↓


改修前の子獅子↑ 改修後の子獅子↓


いやもう、驚くほどの若返りというかアンチエイジングというか、こうして比較して見ると、いかにピカピカになったかがよく分かる。
黒崎嘉門氏は彫刻師だが、彩色もやるのだろうか? それとも仲間に発注したのだろうか?
これはもう、時代を超えた職人たちの「合作」と呼ぶべきかもしれない。
では、ぐるっと回りながらじっくり見ていこう。
前鬼板・懸魚は龍

金ピカに甦った前鬼板と懸魚の龍

前欄間も龍

木鼻の獅子と象


外障子と直高覧は朱漆塗り

外欄間は葡萄に栗鼠


高覧下は波に鴛(おしどり)


波間に牡丹?は珍しい?

(次ページへ続く)
←このテーマでの1つ前はこちら
⇒このテーマでの続きはこちら

たくきのカメラガイドはこちら
『彫刻屋台図鑑01 鹿沼の彫刻屋台』★
ユネスコ無形文化遺産登録で注目が集まる鹿沼の彫刻屋台。全27屋台を128ページフルカラーで「アート」として見つめ直す写真集。
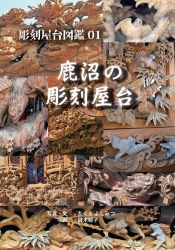
B6判・128ページ フルカラー オンデマンド 無線綴じ
1280円(税別) 送料:160円
■ご案内ページは こちら
こちら
更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報
Twitter
 books
books
 music
music
 目次
目次
 HOME
HOME
 一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ
一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ